水族館の癒しスポットであり、映えスポットでもあるくらげの展示。
様々な種類がいて数多くの水族館で展示されていますが、皆さんはくらげの生態は知っていますか?
今回はミズクラゲを例に紹介していきます!
くらげはプランクトンの一種で、ミズクラゲはその中でも刺胞動物に分類されます。
刺胞動物とは触手があり、その先に毒を注入する針を持つ生き物の事を指します。(イソギンチャクやサンゴ等)
カブトクラゲ等の毒は持たず、粘着物質を出す種類は有櫛動物に分類されます。

ゼラチン質の体の95%以上は水分でできており、脳も心臓も血管も無く点眼と呼ばれる目のようなものはかろうじて明暗が分かる程度です。
そんな体でどうやって生きているのだろう?と思いますよね。口と花びらの様に見える胃腔(胃袋)、水管(血管のようなもの)があるので、体中の神経や触手で獲物を察知して食べ胃腔で消化したり、傘を動かして水管を通し体内に養分を循環させたりと生きていくのに必要な器官は揃っています。
くらげはプランクトンの仲間だったり、ほとんど水分でできていたりと面白い生態をしていますが、生まれてから生体になるまでの過程も面白いのです!
オスメスの有性生殖により受精卵ができ、受精卵が細胞分裂を繰り返し「プラヌラ」と呼ばれる0,2~0,5㎜ほどの幼生になると付着しやすい岩や貝殻などに付きます。
 (岩に付着したポリプ)
(岩に付着したポリプ)
岩等に付着すると0,5~1㎜ほどの「ポリプ」と呼ばれるイソギンチャクのような形に姿を変え、触手を使ってプランクトンを捕食しながら成長していきます。
ポリプから成長していくと体に少しずつくびれができていき、「ストロビラ」になります。
ストロビラが無性生殖をし自分のクローンを増殖させ、体のくびれが深くなり分裂し2㎜ほどの「エフィラ」と呼ばれるくらげの赤ちゃんになります!

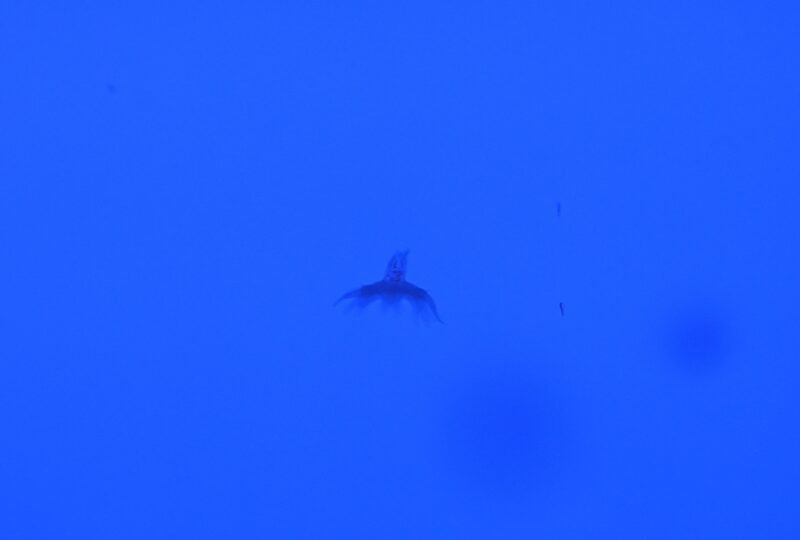 (頑張って泳ぐエフィラ)
(頑張って泳ぐエフィラ)
受精卵→プラヌラ→ポリプ→ストロビラ→エフィラ(赤ちゃん)→メデューサ(大人)
ここまでくるのに数年かかるのに、「メデューサ」と呼ばれる成体になってからの寿命は1年ほどしかありません。
くらげの生態も何度も姿を変えて成長していくのも面白いですよね!
種類によって姿が違い、見た目も興味深いですが成長過程も種類によって違うこともあるので是非調べてみて下さい!


コメント